目次へ
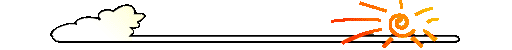
久米島での住民虐殺 1945(昭和20)年6月25日、沖縄における日本軍の組織的作戦は終わったとされています。 ところがその後も戦闘があったことをご存じでしょうか。 しかもそれは、住民を巻き込んだ惨いものとなってしまったのです。 久米島守備隊の鹿山隊長は、いったん降伏を受け入れた。 しかしそれを翻し、「最後の一人になるまで、捕虜になることなく戦え」と命令をくだしました。終戦間際の6月27日に住民をスパイ容疑で住民を殺害したのをはじめ、確たる証拠も無く、また正規の軍法会議にかけることもなく、婦女子も含めた処刑を行いました。それは理性を失った、「虐殺」とよぶに相応しいものであったそうです。 1974(昭和49)年、地元の有志によって「痛恨の碑」が建てられました。 久米島在住の佐久田氏は語りました。 「鹿山隊長は1人ではなかった…。日本国民は全員“鹿山”であった。それはあの戦争の時代のなせることだった。鹿山隊長だけを責めることはできない」と。 痛恨碑を前にして 日本は、負け方を知らなかったようです。 「最後の1人になるまで、捕虜になることなく戦え」の教育は、軍人はもとより、一般住民に至まで浸透していました。「生きて虜囚の辱めをうけず」(戦陣訓)や、鬼畜米英思想や敵愾心などの、徹底した洗脳教育があったのですから。 勿論、異を唱える者もいましたが、それらは国賊やスパイの濡れ衣を着せられて処刑されました。負け方を知っていれば、各地での惨劇も防げたのではないのでしょうか。 命令を下した者を含めて兵隊達は、召集される以前は良き夫であり、よき父であったに違いありません。しかし戦争という極限の状況下では恐ろしいこともしでかしてしまいます。 昔の人は言いました。「心には鬼と仏と相住めり」と。 戦争は理性の喪失に以外の何ものでもありません。そもそも理性が問題です。理性など、あって無いよう曖昧のものですから。 理性の崩壊を森達也氏は次のように鋭く指摘します。 「(私やあなたという、本来)1人称であるはずの主語が、『うち』とか『我々』とかの複数名詞になり、そうなると当然ながら述語は暴走する。『許さない』とか『恨みを晴らせ』に短絡する」 「戦争の世紀を超えて」講談社 森達也・姜尚中共著より 「ぬち(命)どう宝」。 それは、“鉄の暴風”といわれた想像を絶する攻撃を受け、多大な犠牲者を出した戦禍をくぐった沖縄の人々の、心からの叫びなのです。 (おわり) |
