
目次へ
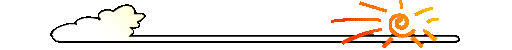
首里城 守礼門 世界遺産にも登録されている首里城は、かつての琉球王朝の城下町首里の小高い丘の上にあります。といっても町中です。戦災で消失しました。現在の建物は1992年に再建されました。以外と最近なんですね。 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 琉球は交易国家でありました。大和言葉の挨拶が「めんそ〜れ」の現在の方言として形を変えながらも残っているという事を見ても、広い繋がりがうかがい知ります。 首里城本殿 中央の赤い道を「浮道(うきみち)」といい、 国王や中国の使者【冊封使(さっぽうし)】等 限られた人だけが通ることを許された。 特に大陸との繋がりは強固なものでした。往来がある故に文化面での共通点も多いです。例えば首里城や守礼門の装飾。この色彩は大陸のそれでありましょう。また、国王即位の際には大陸王朝に挨拶に向かったとのこと。明や清王朝と懇意にすることによって、琉球の中立と平和を維持していたそうです。何しろ戦後「本土復帰」と聞いた市民は、「日本」に復帰するとは考えずに、「中国」に復帰すると思ったとか(首里城公園内の展示資料による)。 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 琉球は相互理解と外交努力によって、軍隊による強固な鎧を着るという選択をしなかった国家だったのです。その為に発展したのが芸能。大陸からの使節団を歌や踊りの芸能でもてなし、それこそ「国益」探り、平和を求めたのです。それは沖縄舞踊や民謡となって、現在も人々の心を和ませています。サンシンが奏でる民謡はとっても良いんですよねぇ。 また国王の平和を求める心は、日本(現在の“本土”)から渡来した仏教僧侶を優遇して、お寺を建てさせたそうです。その頃には浄土真宗の教えも伝わりました。念仏踊りが変化してエイサーとして残っているとも言われています。 1609年に薩摩藩による琉球侵攻によって、王朝体制を維持させられたままに、交易による利益を吸い上げられました。また、同藩による念仏弾圧によって、伝わっていた仏教も表舞台からは姿を消し、鹿児島の隠れ念仏のように密かに代々語り伝えられるようになっていったと想像されます。 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ さて21世紀の現在。もう散々殺し合いの歴史を繰り返してきた我々人間は、琉球やコスタリカ(こちらの頁参照)のような平和への方法も検討する時代じゃないでしょうか。いがみ合いを何時までやってんだろ。本当に人間という生き物は“愚か”。そして人間の私。 Q:世界で唯一、他の生き物が絶滅する 原因になっている生き物は何でしょうか? このパネルを開けるとご覧いただけます。 A:あなたです(鏡がありました)。 ≪某水族館にて≫ (つづく) |
